岡山大学名誉教授
阿部 康二 先生
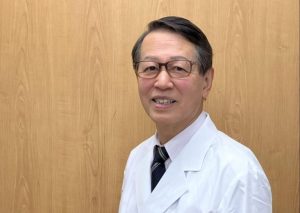
「面白い」という純粋な探求心は、時として世界を変える大きな発見へと繋がります。脳神経内科の世界的権威である阿部康二先生は、まさにその探求心で研究の道を突き進んできました。その結果、脳卒中や難病ALSに対する世界初の治療薬が誕生するなど、数々の画期的な成果を生み出しています。
「行き当たりばったりだった」とご自身のキャリアを振り返る言葉には、常識を疑い本質を追求する研究者の哲学が凝縮されていました。今回は阿部先生に、その型破りな研究者人生の軌跡と、世界を驚かせた発見の核心について詳しく伺いました。
―阿部先生が研究者の道に進んだ経緯を教えてください。
阿部先生:実はそれが難しい質問でね、僕はもともと医者になりたいと思って医学部に入ったわけじゃないんですよ。父が学校の先生だったんですが、高校生の時に模擬試験を受けたら、たまたますごく成績が良くて。それが理由で東北大学医学部を受験したんです。未熟な若者の単純な冒険心だったのかも知れませんね。だから、この話はあまり書かれると困るんだけどね(笑)。当時はそういうことが許された時代だったのかも知れません。
そんな動機だから、大学の授業は本当につまらなかった。教科書に書いてあることを、先生がそのまま黒板に書き写すだけでしょう。それなら自分で教科書を読めばいいじゃないですか。だから大学時代はほとんど学校に行かなかったし、成績もかなり悪かったと思いますよ。
でも、大学を出てから2年間、内科で研修医として働いて、現場で患者さんを診るのは面白いなと感じました。そして、その後の大学院が僕の人生を大きく変えましたね。
大学院で「研究」というものを初めてやったんですが、これがもう、めちゃくちゃ面白かった。大学の授業というのは、誰かがすでに作り上げたことを学ぶだけの『Learn(学習)』です。でも、大学院の研究は、誰も知らないことを自分で作り出していく『Creation(創造)』なんですよ。人間として生まれて、何かをクリエイトできるっていうのはすごく楽しい。絵描きさんや音楽家、小説家もきっと同じでしょう。僕はその面白さに、すっかりのめり込んでしまったんです。
だから、大学院に入ってからは人が変わったように研究しました。大学時代はろくに授業にも出なかった僕が、論文をたくさん書いてね。おかげで同級生の中では一番早く、41歳で教授になりました。昔の僕を知っている同級生はみんな、「大学にも来なかった阿部君が、どうしちゃったんだ?」って、ものすごく驚いていましたよ。
僕にとっては単純な話で、つまらないことはやらない、面白いことには夢中になる。当たり前のことですよね。学生さんに「つまらない授業でも出てこい」なんて、自分に嘘をつくようで僕には言えません。
そもそも脳神経内科を選んだのも、実に行き当たりばったりでね。学生の頃は心臓カテーテルをやる循環器内科に興味があったんです。でも研修でやってみたら、楽しいんだけど3ヶ月で飽きちゃった。病気の種類が狭心症、心筋梗塞、心不全くらいしかなくてね。飽きっぽい僕には、一生やる仕事じゃないな、と。
脳外科も面白そうだなと思ったけど、手術が15時間とか平気であるでしょう。これじゃあ、大好きな酒を飲みに行けないなと思ってやめました(笑)。
その点、脳神経内科は脳の病気を扱いますが、内科だから手術に縛られない。そんな流れで選んだだけなんです。研究をやるつもりも全くなかったのに、教授に「君、大学院に入りなさい」と言われて、「大学院って何やるんですか?」「バカ者、研究するんだよ」って。それで「はい、やってみます」と。本当に計画性がないでしょう。
でも、そうやって始めた神経内科が、すごく面白かった。脳卒中や認知症のように患者さんが多い病気もあれば、数万人に一人というような珍しい病気もたくさんある。なんでこんな病気になるんだろうって、まるでミステリー小説の謎を解くような面白さがあるんです。
結局、僕はその場その場で「面白い」と感じるものに飛びついて、ここまで来ただけ。本当に、行き当たりばったりな人間なんですよ。
―阿部先生の研究について詳しく教えてください。
阿部先生:僕の研究の始まりは、実は細胞膜だったんです。生命というのは、膜で囲まれているからこそ一つの生命体として存在できる。その膜は、外界と情報をやり取りするための「柔らかさ」と、生命を守るための「硬さ」という、相反する性質を両立させなければいけません。
その絶妙なバランスを保つために重要なのが、膜に含まれる「不飽和脂肪酸」なんですが、こいつは非常に酸化しやすい。つまり、生命活動の根本には、常に「酸化ストレス」との戦いがあるわけです。特に脳卒中のように急激なダメージが加わると、膜はボロボロに破壊され、大量の酸化ストレスにさらされてしまう。この酸化ストレスから膜を守ることが、治療の鍵になるんじゃないかと考えたんです。
そんな研究をしていた大学院1年生の頃、今から40年も前ですが、当時の教授から「エダラボンという新しい抗酸化薬があるから、これで研究してみないか」と言われましてね。正直、最初は乗り気ではなかったのですが、やってみたら驚きました。脳卒中を起こしたネズミの脳梗塞が、目に見えて小さくなるんです。「これは面白い」と思いました。
この「エダラボン※1」は、当時全く無名の、日本で生まれた化合物でした。私の師匠である小暮久也先生が酸化ストレス研究の第一人者だった縁で、製薬会社から大学に持ち込まれた、まだ試薬の段階のものだったんです。
この研究成果を、私が初めて『Stroke』という脳血管疾患に関する研究を対象とした国際的な雑誌に発表しました。それがきっかけとなって、「じゃあ、人で臨床試験をやってみよう」という話に進んだ。そして、人でも効果が証明され、2001年に世界で初めて、脳卒中に対する「抗酸化療法」の治療薬として承認されたんです。まさに、新しい治療の扉が開いた瞬間でしたね。
さらに、私はALS(筋萎縮性側索硬化症)※2 という難病にも、この酸化ストレスが深く関わっていると考えていました。そこで、エダラボンをALSの治療に応用できないか、臨床試験を主導することにしたんです。ただ、この時、アメリカではすでに50種類もの薬がALSの臨床試験で試され、そのすべてが失敗していました。私はその失敗の原因を分析して、あることに気づいたんです。「これまでの研究者は大雑把だな」と。ALSという病気は、人によって進行するスピードが全く違う。それなのに、彼らは進行が速い人も遅い人も全部ごちゃ混ぜにしてデータを取っていた。これでは薬が効いているのか、もともと進行が遅いだけなのか、判断できるわけがありません。
そこで私は、全く新しいやり方を提案しました。まず、患者さんに集まってもらい、薬を使わずに3ヶ月間、進行の様子を観察するんです。そして、その期間に「ある一定の速度で病気が進んだ人」だけを、実際の臨床試験に参加してもらう。つまり、病気の進行スピードをきれいに揃えたわけです。
そうしたら、結果はバッチリ。エダラボンの効果が明確に証明され、2015年、ALSの進行を抑える世界初の治療薬として承認されました。
脳卒中にしてもALSにしても、エダラボンはすべて日本で開発され、日本の研究データで世界で初めて承認された「日本ファースト」の薬です。よく「なぜ成果を出せたのか」と聞かれますが、運が良かっただけですよ。ただ、ALSの試験に関しては、これまでのやり方を疑い、勝つための戦略をしっかり立てた。そういう臨床試験のやり方の先鞭をつけられたのは、画期的だったと自負しています。
※1 エダラボンは、活性酸素による酸化ストレスを除去して脳や神経を守る薬で、主に脳梗塞の急性期やALS治療で使われます。阿部康二先生はエダラボンの開発、とくに急性期脳梗塞における神経保護効果の実用化に中心的な役割を果たされました。
※2 筋萎縮性側索硬化症 (ALS) は、運動ニューロンが徐々に破壊されることで、手足や喉、舌の筋肉、呼吸に必要な筋肉が衰えていく病気です。筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かす神経(運動ニューロン)が障害されることで起こります。
―阿部先生はTwendee Xを用いた研究もされていらっしゃると思いますが、どのような経緯で始まったのでしょうか?
阿部先生:私が岡山大学 脳神経内科で教授をしていた頃、「日本認知症予防学会」が立ち上がり、私はエビデンス委員長を任されました。そこで、認知症に効果がありそうな医薬品やサプリメントを全国から公募したんです。その時に、犬房春彦先生から「Twendee X(トゥエンディエックス)」という抗酸化サプリメントの提案がありました。
長年、抗酸化療法をやってきた私としては、犬房先生の研究データを見て「これは50%くらいの確率で効くかもしれないな」と直感しました。そして学会を挙げて臨床試験に取り組んだんですが、その結果には本当に驚かされました。キーオープン(結果発表)した時には、その場にいたみんながどよめきましたからね。予想をはるかに上回る効果が証明され、学会で初めて「グレードAでのエビデンス認定」されたんです。
このサプリの何がすごいかというと、一つ一つの成分はありふれたものなのに、犬房先生の絶妙な「配合の妙」によって、世界最強クラスの抗酸化力を生み出している点です。医薬品は単一の成分でなければなりませんが、サプリメントは多剤を組み合わせられる。その利点を最大限に活かして、単剤では決して届かない高い効果を実現した。しかも、もともと体にあるような安全な成分ですから、副作用の心配もほとんどない。これは素晴らしい発明ですよ。
実は、この研究は、近年の認知症に対する考え方の変化とも深く関わっています。私が学生だった40年前、アルツハイマー病は「脳細胞」の病気、血管性の認知症は「脳血管」の病気で、これらは全く別物だと習いました。教科書にも「日本にはアルツハイマー病はほとんどいない」と書かれていたくらいです。
しかし、高齢化が進んだ今、この常識は完全に覆されました。今のアルツハイマー病の患者さんのほとんどは、血管の老化、つまり動脈硬化を伴っています。つまり、二つの病気がオーバーラップしているんです。血管が老化すると、脳の血流が悪くなり、常に酸化ストレスにさらされるようになります。すると、脳のゴミである「アミロイドβ」がたまりやすくなる。さらに悪いことに、このアミロイド自体が酸化ストレスを発生させるので、悪循環に陥ってしまう。
本来、アミロイドは誰の脳にもできますが、健康な血管ならゴミとしてちゃんと排泄できるんです。しかし、血管が老化して「ゴミ出し」ができなくなると、脳がゴミ屋敷のようになってしまう。これが、現代のアルツハイマー病が増え続けている大きな原因だと私は考えています。
この考え方を広めるために、私は15年前に「日本脳血管認知症学会(Vas-Cog Japan)」という学会を立ち上げましたが、この学会は年々大きくなって来ています。アミロイドβだけを研究している人たちは、血管のことを余り考えない。だから「アミロイドβさえ取れば治る」と信じている。でも、最近出てきた高価な新薬も、アミロイドは劇的に減らすけれど、症状は進行を少し遅らせる程度でしょう。アミロイドβを取り除くだけでは根本治療にならないことが、もう証明されているんです。
では、これからどうすればいいのか。
一つは、病気になる前から使えるサプリメントの活用です。医薬品は病気になってからしか使えませんが、サプリなら若いときから予防的に始められる。これは大きな強みです。
そして何より重要なのが、ライフスタイルです。50歳を過ぎたら、高血圧や高脂血症、糖尿病などをきちんと管理し、適度な運動と社会活動を続ける。お酒はほどほどに、タバコはやめる。体の中に酸化ストレスをため込まない健康的な生活を送る。これが、認知症を防ぐための基本中の基本です。
認知症の患者さんは、今後も増え続けるでしょう。一人暮らしで発見が遅れるケースも多いので、潜在的にはもっといるはずです。だからこそ、アミロイドβだけに目を向けるのではなく、その根本にある「血管の老化」と「酸化ストレス」にアプローチしていく。この「側面射撃」とも言える考え方が、これからの認知症治療と予防において、ますます重要になってくると確信しています。
―最後に、阿部先生が若い研究者の方々に伝えていらっしゃることはありますか?
阿部先生:よく「どうやって先を見て研究テーマを決めているんですか?」と聞かれますが、とんでもない。私は全く先なんて見ていませんよ。ただ、その場その場で面白いと思うことをやっているだけです。世界的な研究の最先端で求められている課題に解決を与えることは面白いでしょう。
研究というのは、本当に不思議なものでね。一つの疑問を解き明かすと、そこから今度は二つの新しい疑問が生まれてくるんです。二つ解決すれば、次は四つ出てくる。やればやるほど、解くべき謎がどんどん増えていく。
つまり、研究には「終わり」がないんです。キリがない。だからこそ、面白いんですよ。やってもやっても飽きることがない。これが、私が研究を続けて来れた一番の理由でしょうね。
だから、私が学生や若い研究者に伝えるメッセージは、いつも一つだけです。
「面白くなければ、やめていいよ」と。
自分自身がそうだったから、よくわかるんです。嫌なことを無理やりやらされるほど、辛いことはないでしょう。人生は一度きりなんだから、そんなもったいない時間の使い方はしてほしくない。
自分が「これは何だろう?」と心から疑問に思うことを見つけて、それを実験で証明してみればいい。自分の考えが正しかったのか、間違っていたのか、白黒つける。そのプロセスは、誰かにやらされる勉強とは全く違う、自分だけの創造的な活動です。これほど面白いことはありません。
だから、若い人たちには、無理に何かを楽しもうとするんじゃなくて、自分が本当に「楽しい」と思えることを見つけて、それに夢中になってほしい。ただ、それだけですね。
「行き当たりばったりだった」と語る軽やかな言葉とは裏腹に、阿部先生の研究者人生は、常に本質を問い続ける真摯な探求の連続でした。「面白い」という純粋な好奇心を羅針盤に、脳卒中やALSといった難病治療に革命をもたらした功績は計り知れません。
先生が提唱する「血管の老化」と「酸化ストレス」という視点は、増加し続ける認知症との戦いにおいても、予防という新たな希望の光を照らしています。医薬品だけに頼らない多角的なアプローチは、私たちが自らの健康を守る上で大きな指針となるかもしれません。
阿部 康二 先生
岡山大学大学院・医歯薬学総合研究科 脳神経内科学 名誉教授
東京リボーンクリニック銀座院 再生医療統括医師