須田医院
須田 道雄 院長
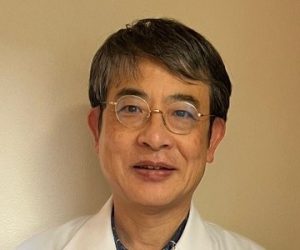
何らかの困った事柄で訪れてこられる方に、医師は「病名」をつけて処方をするだけではなくて、その「病名」が生じるに至った家族や地域での関係性の中での心理的背景と自己認識があるというと、あなたはどう感じますか?島根県大田市で三代にわたり地域医療を支える「須田医院」は、何らかの困った事柄の背景を受け止め、機能を高めていくことのできる医療を目指しています。
院長の須田道雄先生は、内分泌内科医としてのキャリアを経て、心療内科の研修も積まれました。その経験から、来談者の行動の裏にある「本当の想い」を感じ取り、その人らしい生き方をサポートすることを信条とされています。今回は須田先生に、独自の診療スタイルを確立するに至った経緯と、地域医療にかける熱い思いについて、詳しくお話を伺いました。
―須田先生はどのような経緯で開業されたのでしょうか?
須田先生:ここは島根県のちょうど真ん中あたり、世界遺産の石見銀山からも近い場所です。ただ、非常に田舎で人口も少なく、過疎地に近いですね。高齢の患者さんが多い中で、私の代で三代目になります。
もともとこの辺りには医者がいなかったそうで、祖父がこの町に呼び戻されるような形で始めたのがきっかけです。父が二代目、そして私が三代目として跡を継ぎました。
今、私が標榜しているのは内科、小児科、心療内科ですが、実際には小さな外科も含めて「何でも見る」ような、地域の診療所という形でやっています。来られる患者さんは昔からこの町におられる方が主で、中には先代の頃から通ってくださっている方も多くいらっしゃいますね。
私自身は島根医大の卒業です。卒業当時はまだ専門を決めていなかったので、色々な科をローテーションして学べる京都大学の医局に入りました。そこで様々な臓器に関わる「内分泌」を専門に選び、研究では「骨代謝」をテーマにしていました。
京都で診療をする中で、肥満症、糖尿病、甲状腺疾患、あるいは拒食症といった様々な患者さんを診ていると、どうしても心理的なアプローチがないとうまくいかないな、と感じることが多くなりました。そこから興味が湧いて、関西医科大学の心療内科で1年間ほど研修をさせてもらったんです。
その後、地元であるこちらに戻り、大田市立病院で2年間勤務してから、父の跡を継いで開業した、という形ですね。
医師の道に進んだのは、小さい頃から親に「医者の子どもは医者になるんだ」と言われて育ったので、自然と「そうならないといけないのかな」と思っていた部分が大きいです。この地域は医者が少ないので、いずれは自分が帰らないといけないな、という気持ちはありました。
私がクリニックの方針を先代から大きく変えたのは、現代の医療のあり方に疑問を感じていたからです。
きっかけはまた、7年ほど前、インフルエンザワクチンに本当に効果があるのか、地域の小学校でアンケート調査をしてみたことでした。すると、打っても打たなくてもかかる率はほとんど変わらず、中には毎年打つのに毎年かかる子もいました。そこからですね、今の医療は「不安感」によってコントロールされているのではないかと感じ始めたのは。
継承開業後の当初、夜中に電話がかかってくるのは決まって「血圧が上がった」「熱が出た」という相談でした。でも実際は救急の状況ではないことがほとんどで、皆さんすごく心配されている。一人暮らしの不安や家族や周囲との関係性の中での不安感が背景にあると感じました。これではいけないと思い、不安を与えるのではなく、患者さん自身が自分のことを管理し、自分の体を見つめられるような支援の形があるはずだ、と考えるようになりました。
―診療において須田先生が大事にされていることは何でしょうか?
須田先生:私の診療の根幹にあるのは、京都で研修していた頃の経験です。特に心に残っているのが、拒食症の方の治療でした。当時はリストカットをして毎月運ばれてくるような方もいて、従来の治療ではただ体重を増やすだけ、傷を縫うだけで終わってしまいます。でも、それでは根本的な解決にはなりません。
大切なのは、「なぜその行動をとるのか」という背景を考えることです。その方としっかりコミュニケーションをとり、その行動がその人にとってどんな「メリット」になっているのかを一緒に探っていく。そして、その方が「本当はどうありたいのか」を自分自身でイメージできるようにサポートし、それを実現するために自己肯定的な自己対話を継続できるようサポートする。これが本来の医療支援のあり方だと気づいたんです。
そこから、NLP(神経言語プログラミング)※1や催眠療法※2、あるいは自分が望む姿を思い描くイメージ療法※3 などを学びました。また、オウム真理教の脱洗脳をされた苫米地英人博士のメディカルコミュニティーに参加し、認知科学の捉え方を学びました。例えば、これまでの診断は、症状と血液検査、画像データを結びつけて診断しますが、「情報場診断」では、生育歴を含む、他者との関係性の中で、何を思い、何を考えて今の状態に至っているのか、気づいていない情報場を考慮した診断をします。
この考えは、すべての患者さんに応用できると思っています。お薬の継続服用を求めて来院される方も少なくありませんので、関心のない話はしません。より良い未来に関心があり、色々な病院に行っても良くならないような重篤な症状で来られた方には、少し時間をかけて背景をお聞きします。今の状況を一緒に捉え直すことで、薬をたくさん使わなくても良い状態になる方が、実はたくさんいらっしゃるんです。
私が患者さんによくお伝えするのは、「すべての行動には、その人なりのポジティブな意図(メリット)が隠れている」ということです。例えば、拒食症の方がなぜ食べないのかというと、食べないことによって周囲から注目されたり、守ってもらえたりするという、その方なりのメリットがあるからかもしれません。
でも、それは本当に望んでいることなのか。もっと本質的な部分を一緒に考えることで、「本当に自分がしたいこと」が見えてくる。私はそのための選択肢をできるだけ提供し、ご本人が自分で道を選んでいけるような、そんなサポートをしていきたい。
患者さんには、自信を持ってほしいんです。「あなたが今やっていることは、間違っているわけではなく、むしろあなたにとって必要なことだったんですよ」と。そこを原点にして、さらに良い方法があるかもしれない、ということを一緒に模索していく。そんなスタンスで、一人ひとりの「あなたらしい生き方」を支えていきたいと思っています。
※1 NLP(神経言語プログラミング)とは、人間の思考、感情、行動が言語やその他のシンボルによってプログラムされているという考えに基づいた、コミュニケーション、能力開発、心理療法へのアプローチを目指す技法
※2 催眠療法(ヒプノセラピー)とは、催眠状態を利用して、潜在意識に働きかけ、心身の問題解決や自己成長を促す心理療法
※3 イメージ療法とは、心の中で特定のイメージを描き、それを体験することで、感情や思考、行動に変化をもたらす心理療法の一種
―Twendee Xはどのようにして知っていただいたのでしょうか?
須田先生:Twendee Xを知ったのは、全国有志医師の会の勉強会で犬房春彦先生が登壇されて、ご紹介してくださったのが最初です。兵庫県尼崎市でクリニックをされている長尾和宏先生も話されていましたね。その時は主に「ワクチン後遺症」の対策として話を聞いていました。
ワクチン接種後の疾患を診ていると、どれも血管系に何か問題が起こっているなと当初から感じていました。なので、そこにはきっと「酸化ストレス」が影響していて、血管の老化を防ぐ一つの要素として抗酸化作用をもち、飲みやすい錠剤のサプリメントを提供することで症状の改善に向かうのであれば、喜ばしいことであると感じました。
実際に患者さんにご案内したのは、倦怠感や手足の血流障害、しびれといった症状で困っている方々です。特に、ご自身で「これはコロナワクチン後遺症かもしれない」と気づいていて、どこへ行っても良くならないと相談に来られた方ですね。そういう方々にご案内していました。
ただ、私のクリニックではこれまで自由診療をほとんどやってこなかったんです。この地域は田舎ですし、患者さんの多くは自由診療というものを知りません。安価で信頼している保険診療を望まれる方がほとんどです。
ですから、例えば「これは自費で1,000円です」と言っても、その金額が高いと感じる方もたくさんおられます。「保険の中でやってほしい」という方が多いので、なかなか自由診療の形で提供するのは簡単ではありません。
もし、この地域で症状に悩まれている方でTwendee Xを使って「本当に良くなった」という方が一人、二人と出てくれば、そこから口コミで広がっていく可能性はあるかもしれません。ですが、そのためにはまず、この地域の皆さんの意識から変えていく必要があると感じています。
すべてをお医者さんに頼るのではなく、「自分で自分の健康を改善していく」という思いを持つ方が増えてこそ、こうした選択肢も広がっていくのだと思います。Twendee Xが、そのきっかけになっていけばいいなと期待しています。
―最後に、地域の患者さんへ伝えたいことはありますか?
須田先生:今後、医療がどう変わっていくか。それは、医師も来談者も含め、一人ひとりが「どのような情報を得て、どのような視点を持つか」で決まってくるのだと思います。医師の中でも考え方の違いがあるように、来談者の方も、その方がどんな情報を受け入れられるかを見ながら、最適なものを提供できるように努めたいです。
医師の先生方の認識も少しずつでも変わっていけば、サプリメントのようなものも、もっと受け入れられやすくなる日が来るのではないかと期待しています。
地域の皆さんにお伝えしたいのは、まず「自信を持ってください」ということです。人は一人ひとり、物事の考え方も捉え方も違います。今あなたが考えていること、やっていることは、決して間違っているわけではなく、むしろあなたにとって必要であったことなのです。まずはそこを原点として、他者に捉われない自分らしい考えや思いを持ってほしい。その上で、もしかしたらもっと良い改善の仕方があるかもしれない。そこを一緒に見つけ出し、サポートしていくのが私の役割だと思っています。
医療とは、一人ひとりの「あなたらしい生き方」を支えること。私は、そのための選択肢を示し、皆さんと一緒に最善の道を模索していきたいと考えています。
今回は、患者一人ひとりの心に寄り添い、その人らしい生き方を支える須田医院の須田先生にお話を伺いました。先生が実践されているのは、症状だけでなくその人の背景にある情報とその捉え方についても受け止め、共に未来を模索していく、温かくも本質的な医療の姿でした。酸化ストレスをはじめとする新たなアプローチが、こうした先生方の力強いサポートと結びつくことで、地域医療にさらなる希望の光を灯していくのではないでしょうか。

須田医院
〒699-2301 島根県大田市仁摩町仁万862-1
https://suda-c.jp/
医療関係者様向けに、Twendee Xの無償サンプル提供を行っております。
詳細はこちらをご覧ください。